
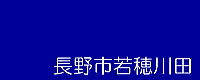

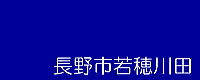
|
北国街道松代道が江戸幕府の道中奉行が管理する街道として建設された当初は、川田宿は国道403号の北側、一里塚跡から西寄りにあったそうです。ところが、千曲川の氾濫によって大きな水害が繰り返されたため、1740年頃(元文から寛文への移行期)に現在地に移転しました。 ◆山麓の高台に移転再建された宿場街◆ |
||
| 目次(サイトマップ) |  川田宿街通りの西寄りからの眺め:江戸時代から街道の幅は12メートル近くあったという |
|
今回の歩きの起点の北東200メートルほどの位置に一里塚跡があるが、これは川田宿の移転前のものだと推定できる。宿場の移転前後の時期には一里塚はさほど重要視されなくなり、平坦地では塚を撤去することもあった。  ▲ここが町川田村の端で、個の草原で二十三夜待ちが催されたか  ▲下横町と呼ばれた街区から街道沿いに南方を眺める  ▲ここで直角に街道は待っていて、石垣を施された桝形があった 角には石垣が向かい合っていて、道幅を狭めていた。今は秋葉社の祠が自然石の搭の上に祀られている。  ▲ここが川田宿の表町通りで、江戸時代から道幅が広かった  ▲宿場街の中央には本陣・問屋・旅籠などの有力商家が並んでいた  ▲本陣西澤家の大きな土蔵に挟まれた重厚な長屋門  ▲江戸時代には高い屋根は草葺(藁葺または茅葺)だった  ▲街道の向かいに残る粗壁土蔵群:旅籠「和泉屋」跡  ▲本町通西端の曲がり角:ここにも石垣桝形があった  ▲石垣跡に自然石の塔台上に秋葉社が祀られている  ▲北に進む道の少し先、上横町の端にも桝形があった 上横町通り西脇――ここが宿場の西端――には松代藩口留番所があった。通行人とその荷物を検問していた。そこを西に過ぎた尾根裾から尾根を越えて大室に向かう峠道があって、その山道が正規の街道だったようだ。 関崎の尾根の麓は千曲川の波が打ち寄せる崖になっていて、危険だった。崖沿いの脇道もあったようだが、たいていの旅人は尾根を越えて大室に向かったらしい。18世紀半ばごろから、関崎では、千曲川両岸を往来する渡し船が利用されるようになったという(関崎の渡しと呼ばれた)。 |
◆繰り返された水害で宿場移転◆
江戸幕府の道中奉行によって川田宿が指定されたのは1611年(慶長16年)でした。その当時には、宿場街の位置は国道403号脇の一里塚跡から300メートルくらい西寄りにあったと伝えられています。今は、田畑のなかに卸売り企業や雲粗衣会社が集まっている場所の南端辺り――のちに古町と呼ばれた――だと見られます。
町川田村という名称は、中世から戦国時代まで山裾に城下街があって、その遺構に集落がつくられたからだと見られます。 ◆美しい景観の表街通りがあった◆ 川田宿で東西の向きになっている旧街道は、本町通り呼ばれていたようです。道幅は7間(12.7m)もあって、中ほどに宿場用水が流れ、その両畔は樹木植栽となっていました。また、各屋敷の前は幅1間くらいの前庭となっていて、そこにもツツジや松、カエデなどが植えられていました。
本町通りの中央北側には本陣西澤家(問屋兼務)の屋敷があって、広壮な蔵に両脇を固められた長屋門が設けられていました。通りに面して西澤家の蔵長屋が約60メートルにわたって続いて、広大な屋敷地を囲んでいたものと見られます。両隣も村役人の屋敷で、それなりの土蔵が通りに面していたはずですから、壮大な眺めの風景だったでしょう。 ◆西端の桝形跡から口留番所跡まで◆ 本町通りが東西に430メートルくらい続いた先で、街道はまたもや直角に北に曲がります。ここにも石垣を施された桝形がありました。
|
|